テレビプロデューサーとして数々のヒット番組を手がけてきた佐久間宣行さんが、自身の働き方やキャリア観を語った一冊『佐久間宣行のずるい仕事術』。
この本は、会社という組織の中にいながらも、自分らしく、無理せずに成果を上げていくためのヒントが詰まっています。
本記事では、本書を読んで考えさせられたポイントを3つに絞ってご紹介し、現代の働き方に対するヒントを探っていきます。
考察① 自分の“好き”を軸にキャリアを築く重要性
やりたいことを仕事にするのは理想だと思いつつも、多くの人が現実とのギャップに悩んでいます。
本書では、「好き」を軸にした働き方の実現が可能であることを、佐久間さん自身のキャリアを通じて伝えています。
彼はテレビ東京という大きな組織の中で、出世や評価を追うよりも、自分の「好き」に従い番組作りを続けてきました。
たとえば、他の人が敬遠するような企画にも積極的にチャレンジし、自分が面白いと思えるものを世に出す努力を惜しまなかったそうです。
このように、「好き」を明確にし、それを仕事にどう落とし込むかを意識することで、働くモチベーションを維持しながら成果を出すことができると感じました。
結果的に、その姿勢が周囲の信頼を集め、やりたいことを形にできる環境を自ら作り上げたのです。
考察② 他人の評価に振り回されず、自分で判断する力
本書を通して印象的だったのは、「他人の目を気にしすぎず、自分の頭で考えて動くことの大切さ」です。
評価や周囲の反応に流されるのではなく、自分が面白いと思うこと、価値があると信じることを信じ抜く姿勢が語られています。
佐久間さんは、ヒット番組『ゴッドタン』や『あちこちオードリー』などを生み出す過程で、周囲の反応に一喜一憂するのではなく、自分が「これだ」と思った方向に進みました。
特に、社内の評価よりも視聴者の反応を重視し、現場で得たリアルな手ごたえを大事にしていたことが印象的です。
この姿勢は、日々の仕事に迷いが生じたとき、自分自身の価値基準を持つことの重要性を教えてくれます。
自分の軸を持っていれば、どんな状況でもブレずに判断し、行動に移すことができるのです。
考察③ 効率よりも情熱が仕事を面白くする
今の時代、「いかに効率的に働くか」が注目されがちですが、佐久間さんの考えはそれとは少し違います。
本書では、「効率だけを追い求めても、面白い仕事はできない」というメッセージが繰り返し語られています。
たとえば、企画書を作るときも、最短ルートで形にするより、自分が納得いくまで試行錯誤することを重視していたそうです。
無駄に見えるプロセスも、良いアイデアを生み出すためには必要であり、それこそが仕事の“面白さ”を生む源泉だといいます。
この考え方は、忙しさに追われる現代のビジネスパーソンにとって、大きな気づきになるはずです。
効率に縛られすぎず、時には寄り道を楽しみながら、自分なりの価値を仕事に込めることの大切さを感じました。
まとめ
『佐久間宣行のずるい仕事術』は、組織に所属しながらも、自分のやりたいことを実現するためのリアルな知恵が詰まった一冊です。
特別なスキルや才能がなくても、自分の「好き」を明確にし、信じる道を突き進むことで、周囲に流されずに働くことができると教えてくれます。
効率化や評価ばかりを追うのではなく、情熱を持って自分らしい仕事に取り組むことの価値を、改めて考えさせられました。
自分の働き方を見つめ直したい方にとって、多くのヒントが得られる内容だと思います。
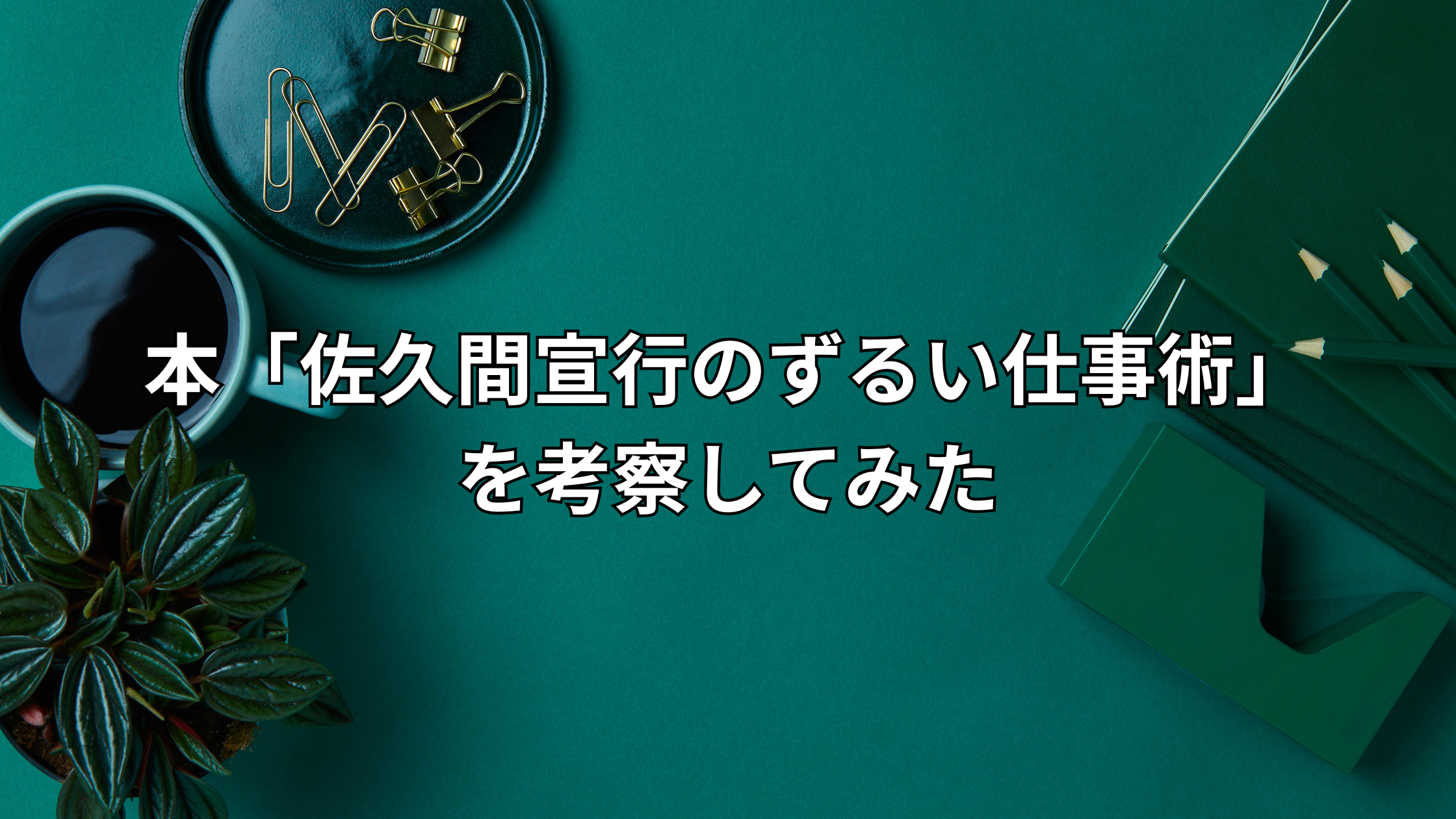
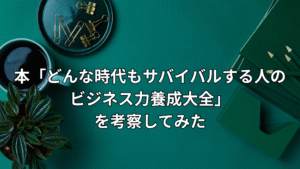
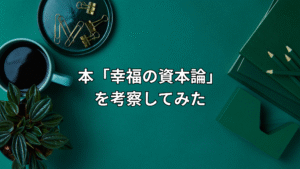
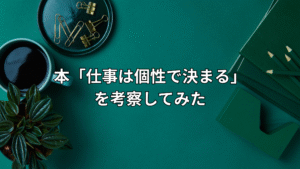
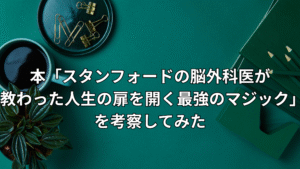

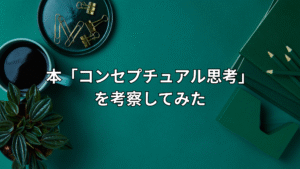
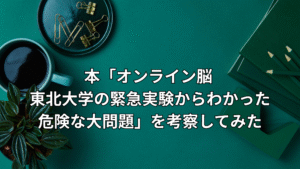
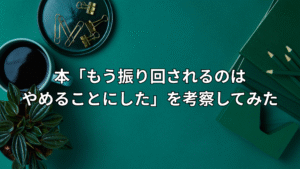
コメント