美濃部哲也さんの著書『仕事の研究』は、働くすべての人にとって「仕事とは何か?」をあらためて問いかける一冊です。
実体験に裏打ちされた内容は、派手さはないものの、じわじわと読者の内面に浸透してくる力を持っています。
本記事では、本書を通じて筆者が感じた3つのポイントを考察としてまとめました。
考察① 「仕事=役割」と捉えることで、迷いが減る
「自分にとって仕事とは何か?」と悩む人は少なくありません。
しかし、本書では「仕事とは社会から与えられた役割」だと語られています。
この考え方は、自分探しの迷路に入り込まず、目の前の仕事に意味を見い出すうえで非常に役立ちます。
たとえば、著者自身が営業職を経験した際、「売上を上げる」というミッションが与えられていたといいます。
そのとき、「なぜ営業なのか」「この仕事にやりがいを感じない」といった思考ではなく、「この役割をどう果たすか」に意識を集中したそうです。
すると、徐々に成果が出て、チームに貢献できる実感もわいてきたと語っています。
「役割に徹する」とは、自分を殺すことではなく、自分の力を今の場所で発揮するという姿勢です。
そのシンプルな視点が、日々の迷いや焦りを減らしてくれるのです。
考察② 本質は「手段」ではなく「目的」にある
本書を通じて繰り返し登場するテーマの一つに、「手段と目的を取り違えないこと」の重要性があります。
どんなに魅力的な仕事であっても、それが目的化してしまえば、やがて違和感が生まれます。
著者は、コピーライターからキャリアをスタートし、次第にマーケティングや経営の領域へと関わるようになったそうです。
その過程で「書くことが目的になってしまっていた時期がある」と振り返っています。
本来は、誰かにメッセージを届け、行動を促すことが仕事の目的であったはずなのに、表現の巧みさや注目されることに執着していたといいます。
これは多くの人にも通じる話ではないでしょうか。
資格を取る、スキルを磨く、肩書きを得る――それらはすべて手段であり、本来の目的に貢献しているかどうかが重要です。
だからこそ、自分の仕事が「何のために存在しているのか?」を見失わないことが、長く働き続けるうえでの軸になります。
考察③ 「動きながら考える」ことの力
現代は変化のスピードが速く、正解のない問いがあふれています。
そんな時代において、著者が提唱する「動きながら考える」という姿勢は、大きなヒントになります。
多くの人が、正しい答えや最適な選択肢を探して立ち止まってしまいがちです。
しかし著者は、「まずはやってみる」「動きながら微調整する」ことで、答えが見えてくると語っています。
実際に、著者が会社を辞めてフリーになった際も、完璧な準備が整っていたわけではありませんでした。
むしろ、不安のなかで動きながら、自分の価値を再定義していったといいます。
この考え方は、挑戦に対する心理的ハードルを下げてくれます。
すべてを決めてから動くのではなく、動くことで選択肢が広がり、視界も開けてくるのです。
まとめ
『仕事の研究』は、派手なノウハウやテクニックを並べる本ではありません。
むしろ、働くうえでの原点を静かに問いかけてくるような一冊です。
「役割に集中する」「手段と目的を取り違えない」「動きながら考える」といった考え方は、どんな職種・業種の人にも通じる普遍性があります。
もし、仕事に対して迷いを感じているなら、原点に立ち返るきっかけとして、本書は大きなヒントを与えてくれるでしょう。
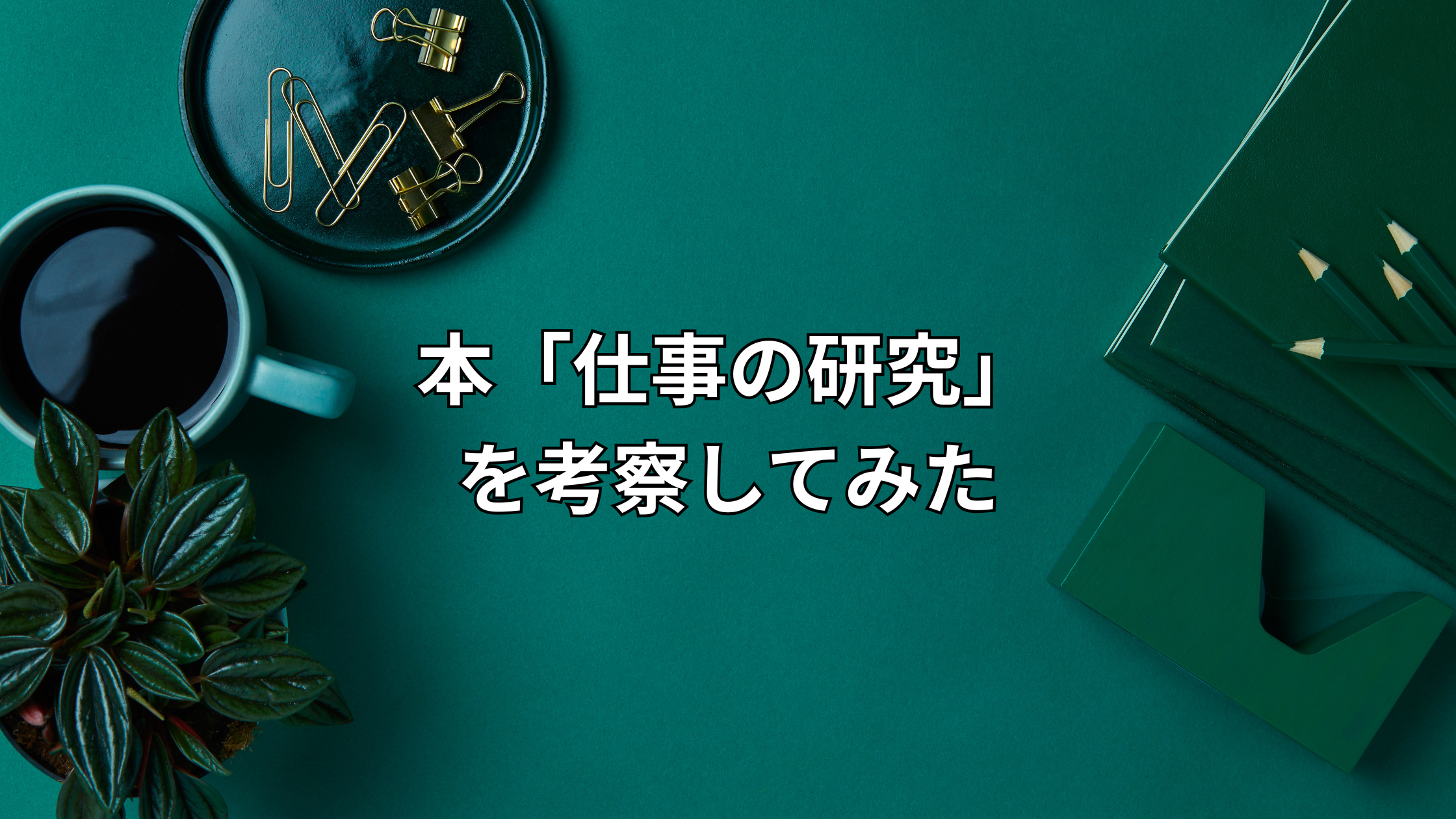
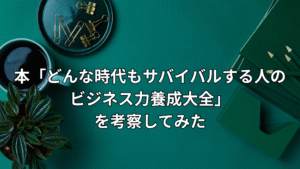
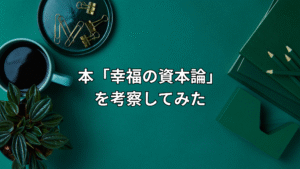
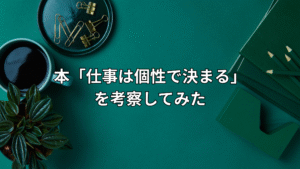
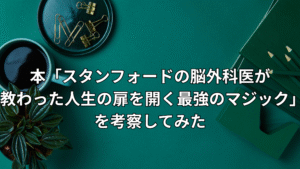

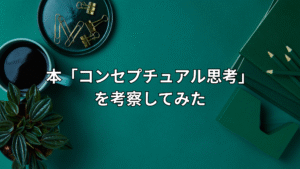
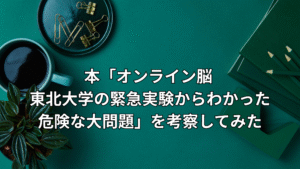
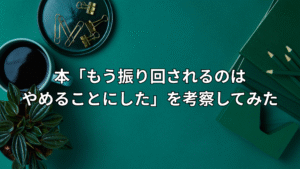
コメント