本書『全米トップ校が教える自己肯定感の育て方』は、ただの自己啓発本ではありません。
スタンフォード大学やハーバード大学といったトップ校で実践されている心理学ベースのアプローチをもとに、「自分を信じる力」を育てる方法が丁寧に紹介されています。
その中でも特に印象に残った3つの考察をまとめました。
考察① 自己肯定感は「結果」ではなく「プロセス」で育つ
自己肯定感は、成功体験の積み重ねによって高まると思われがちですが、本書ではその考え方に一石を投じています。
大切なのは、結果そのものではなく、取り組んだプロセスや姿勢に注目することです。
たとえば、テストで良い点を取ったとき、「すごいね、よく頑張ったね」という声かけは、結果ではなく努力にフォーカスしています。
このような言葉がけによって、子どもや大人は「自分の行動に価値がある」と感じることができ、徐々に自己肯定感を高めていけるのです。
この考え方は、日々の仕事や人間関係にも応用可能です。
たとえ結果が思うようにいかなくても、自分がどんな気持ちで行動したのか、どんな工夫をしたのかに目を向けることが、自分を認める第一歩になります。
自己肯定感を育てるには、成功よりも「取り組みの質」を大切にする視点が必要だと感じました。
考察② 他人と比較しない環境づくりが鍵になる
自己肯定感を低くする最大の原因のひとつが、他人との比較です。
特にSNSが当たり前の現代では、無意識のうちに「自分はあの人より劣っている」と感じてしまいがちです。
本書では、比較の対象を「他人」から「過去の自分」へと変えることが推奨されています。
成長の物差しを他人に預けるのではなく、自分自身の中に持つこと。
それが自己肯定感を安定して保つコツです。
たとえば、「去年よりも落ち着いてプレゼンできた」「前回より早く資料をまとめられた」といった小さな成長に気づくことが、自信を積み重ねる手助けになります。
他人と比べるクセをやめ、自分のペースで成長を認めていく。
それが、ブレない自己肯定感を築く土台になるのだと思います。
考察③ 自己肯定感は「自分との対話」から生まれる
本書で特に印象に残ったのは、「内なる声」との関係についての記述です。
人は1日に数万回の「内的対話」を繰り返しているとされ、その内容がネガティブであるほど、自己肯定感は低下していきます。
このような「セルフトーク(自分への声かけ)」の質を見直すことが、自己肯定感の向上につながるというのです。
たとえば、失敗したときに「自分って本当にダメだな」と責める代わりに、「うまくいかなかったけど、チャレンジした自分は偉い」と認めてあげる。
こうした小さな変化が、自分を信じる力につながっていきます。
実際、ポジティブなセルフトークを習慣化している人ほど、困難に強く、前向きな行動を取りやすいことがわかっています。
自分との対話を整えることが、自己肯定感の「見えない根っこ」を育てるのだと納得しました。
まとめ
『全米トップ校が教える自己肯定感の育て方』を通じて学んだのは、自己肯定感とは「特別な人にだけある力」ではなく、「日々の意識や行動で誰でも育てられるもの」だということです。
結果よりも努力に注目する、他人と比べず自分の成長を見る、そして自分との優しい対話を心がける。
これらを積み重ねていけば、他人の評価に左右されず、自分を信じて前に進む力が自然と育っていくはずです。
自己肯定感を育てることは、よりよく生きるための基盤を築く行為だと改めて感じさせてくれる一冊でした。
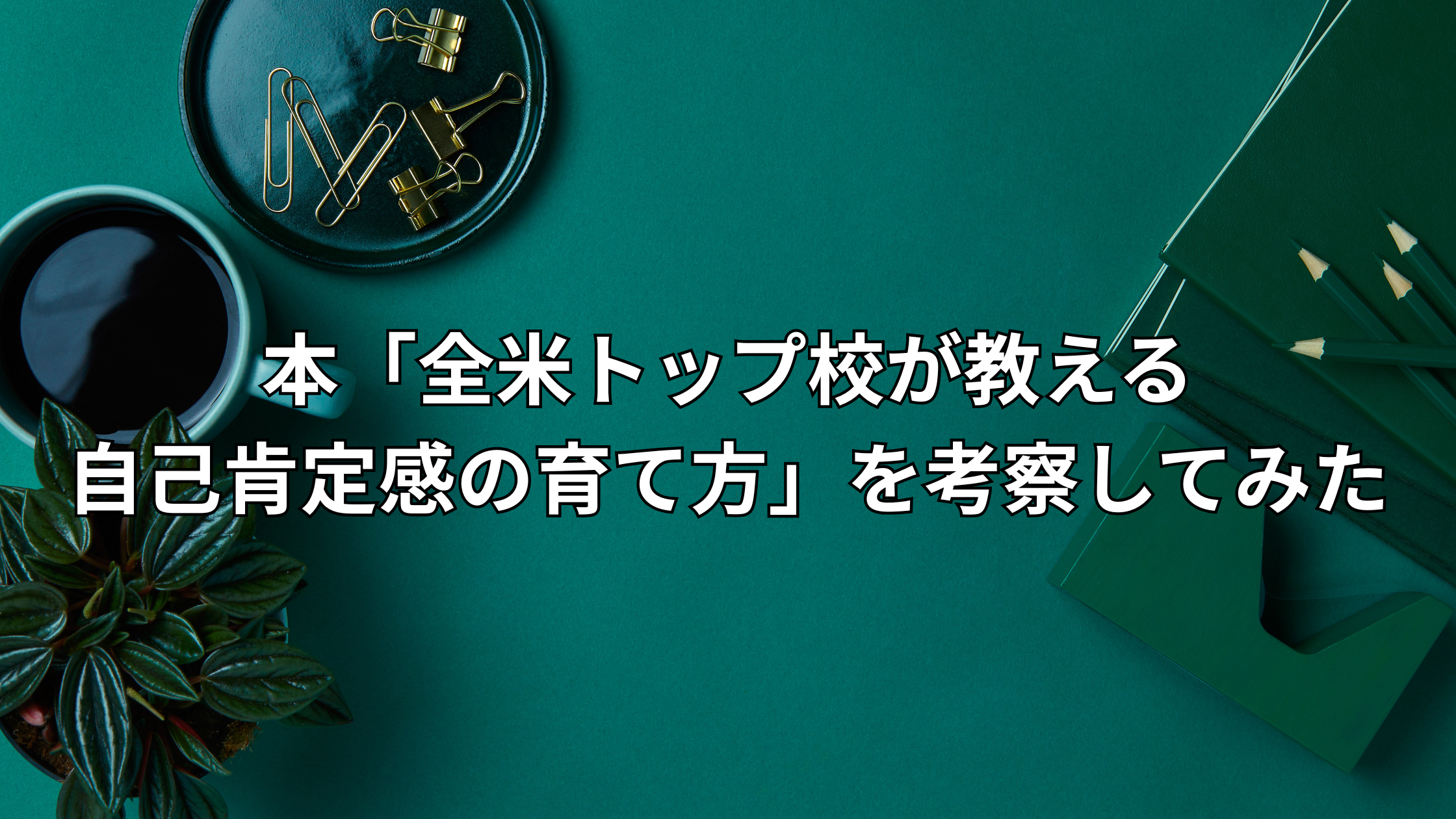
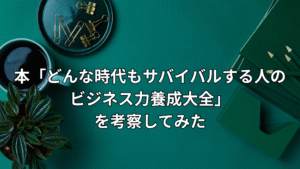
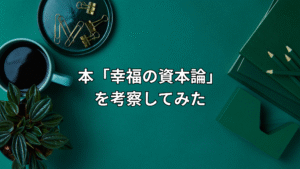
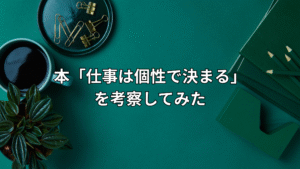
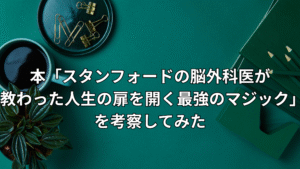

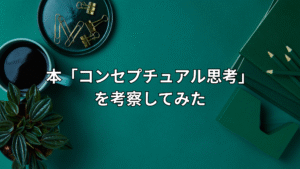
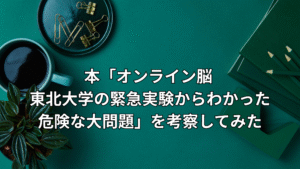
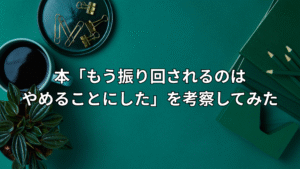
コメント