橘玲さんの著書『幸福の資本論』は、「幸せとは何か」という問いに対して、独自の視点から答えを提示してくれる一冊です。
お金や仕事、人間関係といった、私たちが日々直面するテーマについて、極めて現実的でロジカルなアプローチがなされており、人生を見つめ直すヒントに満ちています。
今回は、本書の考察ポイントを3つに絞って紹介しつつ、その核心に迫ってみたいと思います。
考察① 「幸福」は3つの資本で決まる
本書の中核にあるのが、「幸福は金融資本・人的資本・社会資本という3つの資本で構成されている」という考え方です。
これまで「幸せ=お金」と単純に捉えられがちでしたが、著者は「お金はあくまで一部にすぎない」と断言します。
金融資本は言うまでもなく、お金や資産のこと。
人的資本は、自分の能力やスキル、健康状態を指します。
そして社会資本とは、家族や友人、地域社会などとのつながりのことです。
この三つがバランスよく揃っていることで、初めて「本当の意味での幸福」に近づけるという視点は、非常に示唆に富んでいます。
例えば、いくら金融資本があっても、孤独で不健康であれば、幸福感は得にくい。
逆に、たとえお金が少なくても、信頼できる人間関係や、健康な身体、やりがいのある仕事があれば、人生は豊かになるというわけです。
このフレームワークにより、自分の「足りない部分」が明確になり、今後どこに力を注ぐべきかが見えてきます。
考察② 「働く理由」を問い直す
本書では、仕事の捉え方も大きなテーマになっています。
特に印象的なのは、「仕事はお金のためだけではなく、自己実現や社会とのつながりを得る手段でもある」という指摘です。
日本では「終身雇用」や「年功序列」といった制度が長年続き、個人の意思よりも組織に従う働き方が美徳とされてきました。
しかし現代では、転職や副業が当たり前になりつつあり、「自分はなぜ働くのか」という問いに向き合う必要があります。
たとえば、人的資本を高めるためにスキルアップを目指すことは、自立につながります。
また、社会資本を意識すれば、職場内外での人間関係もより大切にするようになるでしょう。
働く意味を見直すことで、ただの「労働」が、人生を豊かにする「活動」に変わっていくのです。
考察③ 自由になるには「資本の組み合わせ」が鍵
最終的に、著者が強調しているのは「自由に生きること」です。
そのためには、3つの資本をどう組み合わせて活用するかが重要だと説かれます。
たとえば、社会資本が豊かであれば、仮に収入が減っても、助けてくれる人がいる。
逆に金融資本があれば、自分のやりたいことに挑戦しやすくなる。
また人的資本が高ければ、環境が変わっても柔軟に対応できます。
このように、1つの資本に頼るのではなく、複数の資本をかけ合わせることで、「もしも」に強くなれる。
つまり、幸福であることと同時に、「自由」も手に入れることができるのです。
この視点は、変化が激しい今の時代において、自分を守る確かな指針になると感じました。
まとめ
『幸福の資本論』は、「どうすれば幸せに生きられるか?」という普遍的な問いに、非常に現実的で明快なヒントを与えてくれる一冊です。
金融資本・人的資本・社会資本という3つの軸を意識することで、自分の人生に足りないものや、磨くべき領域が自然と見えてきます。
働き方に迷っている人や、将来に不安を抱えている人こそ、手に取ってほしい。
幸福とは、与えられるものではなく、自ら組み合わせてつくりあげるものだと気づかせてくれる、価値ある一冊です。
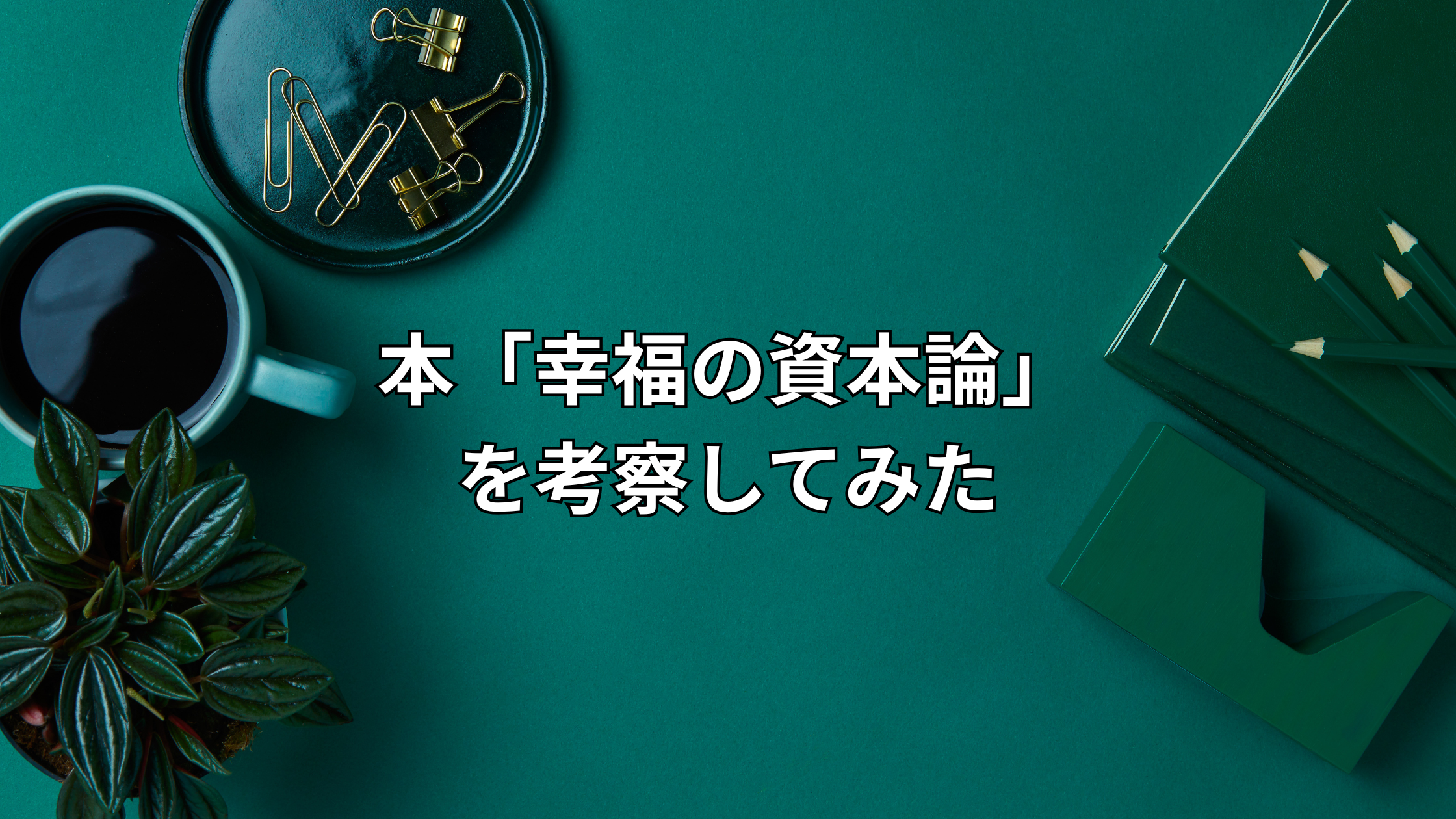
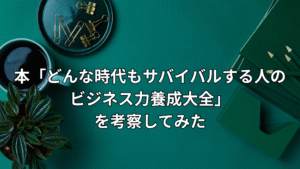
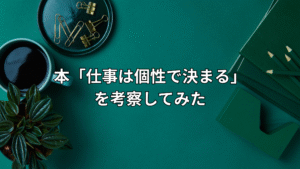
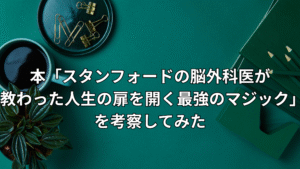

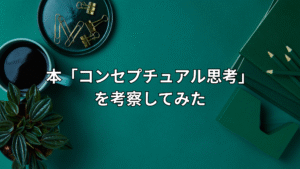
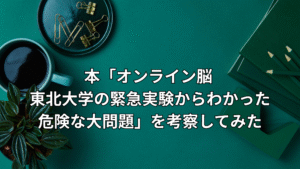
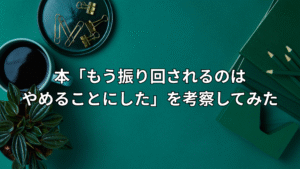
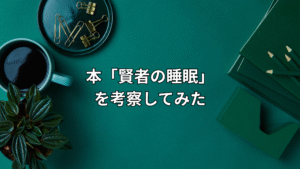
コメント