小林弘幸さんの著書『眠れなくなるほど面白い 自律神経の話』は、普段あまり意識することのない“自律神経”に光を当て、その重要性と整え方についてわかりやすく解説しています。
本書を通じて、自律神経が心身のパフォーマンスにどれほど深く関係しているのかが理解できると同時に、日々の生活を見直すきっかけにもなります。
ここでは、読後の考察として3つのポイントを取り上げ、実生活にどう活かせるかを考えてみます。
考察① 自律神経は「無意識の司令塔」
自律神経は、私たちが意識しなくても24時間働き続けている“自動調整装置”のような存在です。
心臓の鼓動、呼吸、体温の調整、消化、排泄、免疫といったあらゆる生命活動が、この神経系によってコントロールされています。
とくに注目したいのが、交感神経と副交感神経のバランスです。
交感神経はアクセル、副交感神経はブレーキの役割を担っており、このバランスが崩れると、心身に様々な不調が現れます。
たとえば、ストレスを感じたときにイライラしたり、寝つきが悪くなるのは、交感神経が過剰に働いているサインです。
逆に副交感神経が優位な状態が保たれると、リラックスでき、心と体が休まります。
つまり、自律神経を意識することは、体調管理の出発点だと言えるでしょう。
考察② 日常習慣で整えることができる
自律神経は医療の専門領域の話だと思いがちですが、実は生活習慣によって整えることができます。
特別な知識や道具がなくても、自律神経の働きを正常に保つための習慣は、誰にでも取り入れられるものばかりです。
たとえば、朝起きてコップ一杯の水を飲むという習慣は、寝ている間に鈍っていた内臓や神経を優しく目覚めさせてくれます。
また、夜に湯船につかることも効果的です。
ぬるめのお湯に15分ほどつかることで、副交感神経が活発になり、眠りの質も向上します。
このように、ちょっとした生活の工夫だけで自律神経の働きをサポートできるのは、本書が教えてくれる大きな学びの一つです。
考察③ 腸と心のつながりが面白い
本書の中で特に印象的だったのが、「腸内環境と自律神経の相互関係」に関する部分です。
腸は“第二の脳”と呼ばれることもあるほど、多くの神経細胞が集まっており、精神面にも大きな影響を与える器官です。
自律神経が乱れると腸の動きが悪くなり、腸内環境が悪化します。
反対に、腸内環境を整えると自律神経も安定し、心も穏やかになるという相乗効果があるのです。
たとえば、野菜や果物、発酵食品などを意識的に取り入れることで、腸が元気になり、それがメンタルや集中力にも良い影響を与えます。
この考え方を知ることで、ただ“健康に良さそうだから”という理由ではなく、明確な目的をもって食生活を改善する意識が生まれます。
まとめ
『眠れなくなるほど面白い 自律神経の話』は、自律神経という専門的で難解に思われがちなテーマを、驚くほど身近に感じさせてくれる一冊でした。
私たちの健康や心の安定は、自律神経の働きによって支えられていることを改めて実感させてくれます。
そして、それを整える鍵は、特別なことではなく、日々の習慣にあるというのが本書の魅力です。
忙しい日々の中でも、自律神経を意識して生活を少し変えるだけで、心身の調子を整えることは十分に可能です。
「なんとなく調子が悪い」と感じたときは、この本を思い出して、自律神経に目を向けてみると良いかもしれません。
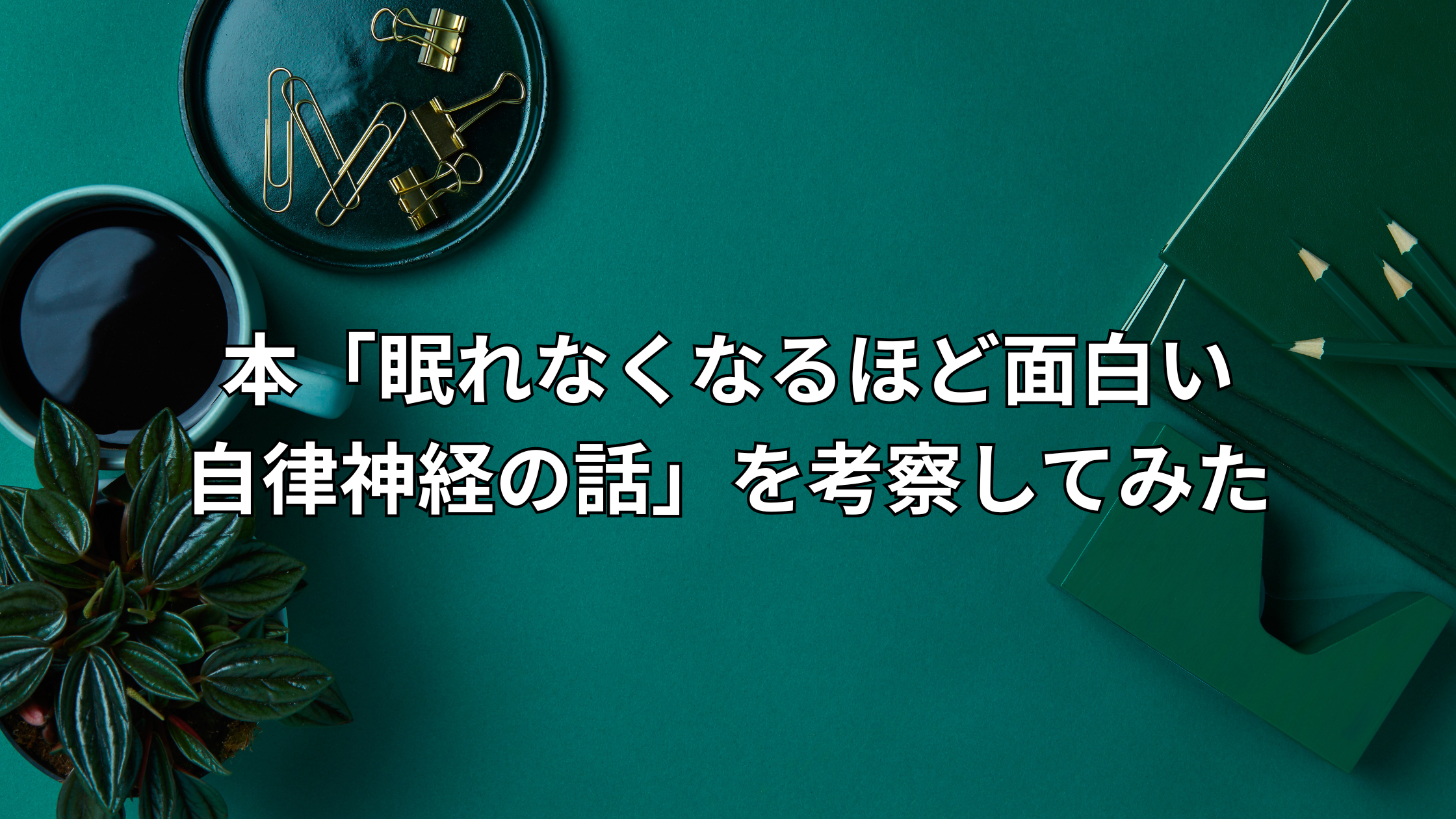
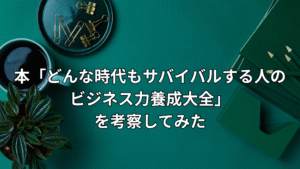
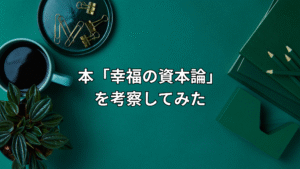
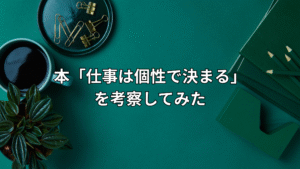
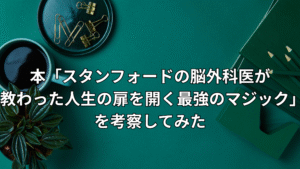

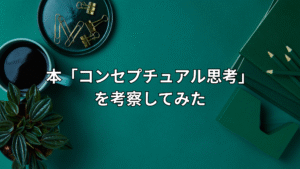
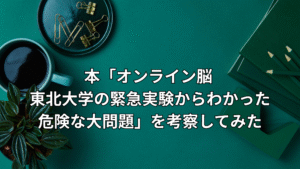
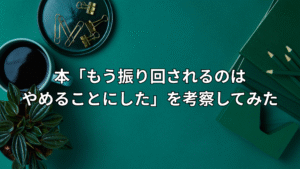
コメント