高砂哲男さんの著書『バランス思考 不安定な社会で成果を手にする』は、変化の激しい今の時代に必要な「しなやかな思考法」を提案してくれる一冊です。
単なる精神論ではなく、思考のバランスを取るための具体的な視点と行動のヒントが詰まっており、個人にもビジネスにも活かせる内容となっています。
考察①:バランス思考は「極端」から自分を守る
この本の核にあるのは、物事を一方向からだけ見るのではなく、両極の間で自分なりの位置を見つけるという考え方です。
社会はどんどん極端化しており、「こうあるべき」という意見がぶつかり合っています。SNSやメディアも、両極の主張を煽るような構造になっており、冷静な判断がしづらい環境です。
そんな時代だからこそ、どちらか一方に偏るのではなく、両方を見たうえで自分のスタンスを決める“バランス思考”が有効です。
たとえば、「仕事は効率重視」か「丁寧さが大事」かという議論も、どちらかに寄るのではなく、状況に応じてバランスを取る視点が求められます。
バランスを取るとは、中庸を選ぶことではなく、極端な意見の間にある“動ける余白”を見つけること。
この視点を持つことで、不安定な社会に流されることなく、自分で選び取る姿勢が持てるようになります。
考察②:インプット力が時代を乗りこなすカギになる
著者が強調するのが、「インプット→プロセッシング→アウトプット」の流れの大切さです。
特に、最初の「インプット力」は情報過多な現代において、ますます重要なスキルになっています。
あふれる情報をただ受け取るだけでは、知識は血肉になりません。
自分に必要な情報を取捨選択し、深く理解する力こそが、本当に“使える知見”につながります。
たとえば、ニュースをただ見るだけでなく、「これは誰の視点で語られているか」「なぜこう伝えているのか」といった視点で受け止めることで、思考の厚みが変わってきます。
また、本や記事を読んだあとに、自分の考えを書いてみるだけでも、理解が深まるのを実感できます。
情報を単に消費するのではなく、自分の中で育てていく。
これが、インプット力を高め、成果につなげるためのポイントです。
考察③:成果は「いいとこどり」で生まれる
本書では、「いいとこどり社会」という印象的な言葉が登場します。
これは、複雑で矛盾する要素が混ざり合う社会において、“どちらかを選ぶ”のではなく“いいとこどり”をして成果を出すという姿勢を指しています。
たとえば、「安定した働き方」か「自由な働き方」かという選択も、どちらか一方を選ばず、会社員として働きながら副業をするという形で両立する人が増えています。
これも、いいとこどりのひとつです。
バランス思考は、矛盾する価値観をうまく組み合わせて、そこから新しい成果を生み出す視点でもあります。
一見すると相反するように見えるものを、どう活かすか。
この柔軟さが、これからの社会での成功を左右するのかもしれません。
まとめ
『バランス思考』は、極端な意見が飛び交う時代にあって、落ち着いて物事をとらえるための「視点の軸」を与えてくれます。
自分なりのバランスを見つけることで、情報に流されることなく、柔軟に成果を出せるようになるのです。
不確実な時代を生き抜くには、ひとつの正解を求めるよりも、さまざまな視点を持ち、自分で“いいとこどり”をしていく力が問われている。
そのヒントが詰まった一冊として、本書は多くの人にとって価値ある指南書になるはずです。

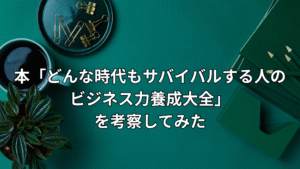
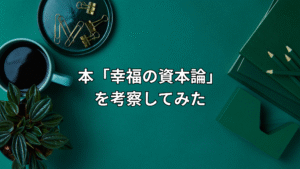
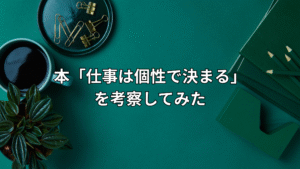
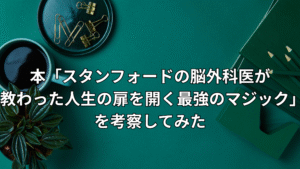

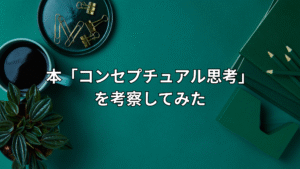
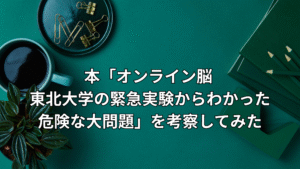
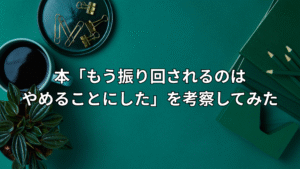
コメント