「教祖になることで夢が叶う」という衝撃的な切り口で語られる『完全教祖マニュアル』は、一見ふざけた本のように見えるかもしれません。
ですが読み進めるうちに、私たちが普段見過ごしている“信じる力”や“人の心の動き”について、深く考えさせられる内容が詰まっていることに気づきます。
ここでは、この本を通じて見えてくる現代社会の構造や人間心理について、3つの観点から考察してみたいと思います。
考察① 信じる力は誰にでもある
人は案外、簡単な理由で“信じる”ことができる生き物です。
この本では、教祖が神を創り、教義を定め、それに従って人々を導いていく過程が描かれています。
その中で面白いのは、教義が本物かどうかよりも、それを信じる人がいることの方が重要だという点です。
例えば、「宇宙のエネルギーとつながる」など、非科学的な内容であっても、それによって安心感を得たり、人生の指針を持てたりするなら、人はそれを信じることができます。
つまり、“信じたい”という気持ちがあるからこそ、信じられるのです。
この構造は宗教に限らず、ビジネスやエンタメの世界にも応用されています。
ブランドやキャラクターへの信頼感も同じ心理が働いています。
信じる力は一部の人に備わっている特別な力ではなく、誰もが持つ普遍的な人間の性質なのです。
考察② 教義はシンプルなほど強い
教義づくりについて本書が強調しているのは、「とにかくわかりやすく」「曖昧さを残す」こと。
この一見矛盾した指針が、実は非常に効果的です。
複雑すぎる教えは人に理解されず、広がりにくい。
一方で、あまりに明確すぎると反論の余地が生まれやすく、反発も生まれてしまいます。
たとえば「感謝すれば幸せになる」という言葉は、一見当たり前ですが、そこに正解や不正解はありません。
誰にでも理解でき、かつ深読みもできる。
だからこそ多くの人に受け入れられやすいのです。
このように、シンプルだけれど意味深長に感じられる言葉こそ、人を惹きつける力があります。
それは宗教だけでなく、自己啓発書や広告コピーにも通じる“言葉の技術”です。
考察③ 教祖は人を幸せにする存在になりうる
本書の最大の皮肉であり、核心部分はここにあります。
教祖=人を操る存在、という悪いイメージを抱く人も多いかもしれません。
しかし著者はあえてこう言います。
「信者が幸せなら、それでいいじゃないか」と。
たとえ教義が空想であっても、信じることで前向きになれるなら、それは立派な価値のある行為です。
また、世の中に不安や孤独を抱える人が多い中で、心の拠り所を提供することは、社会にとって必要な役割ともいえるでしょう。
現代は価値観が多様化し、何を信じればいいのかわかりにくい時代です。
だからこそ、自分の信じるものを見つけた人は、それだけで強い。
その“信じるきっかけ”を提供できる存在は、宗教であれビジネスであれ、社会にとって意味があるといえるでしょう。
まとめ
『完全教祖マニュアル』は、その過激なタイトルとは裏腹に、人間の本質や社会構造をユーモラスに、そして鋭く描き出した一冊です。
信じる力の源、教義の伝え方、人を導く存在の意味。
それらを“教祖”というフィクションに見せかけて、実は現実社会のあらゆる場面に共通する構造として示してくれます。
この本が示すのは、情報があふれる現代において「何を信じるか」「誰についていくか」を選ぶのは、常に自分自身であるということ。
信じるという行為に無自覚なまま流されるのではなく、その仕組みを知ったうえで選べる人でありたい――そんな気づきを与えてくれる一冊でした。
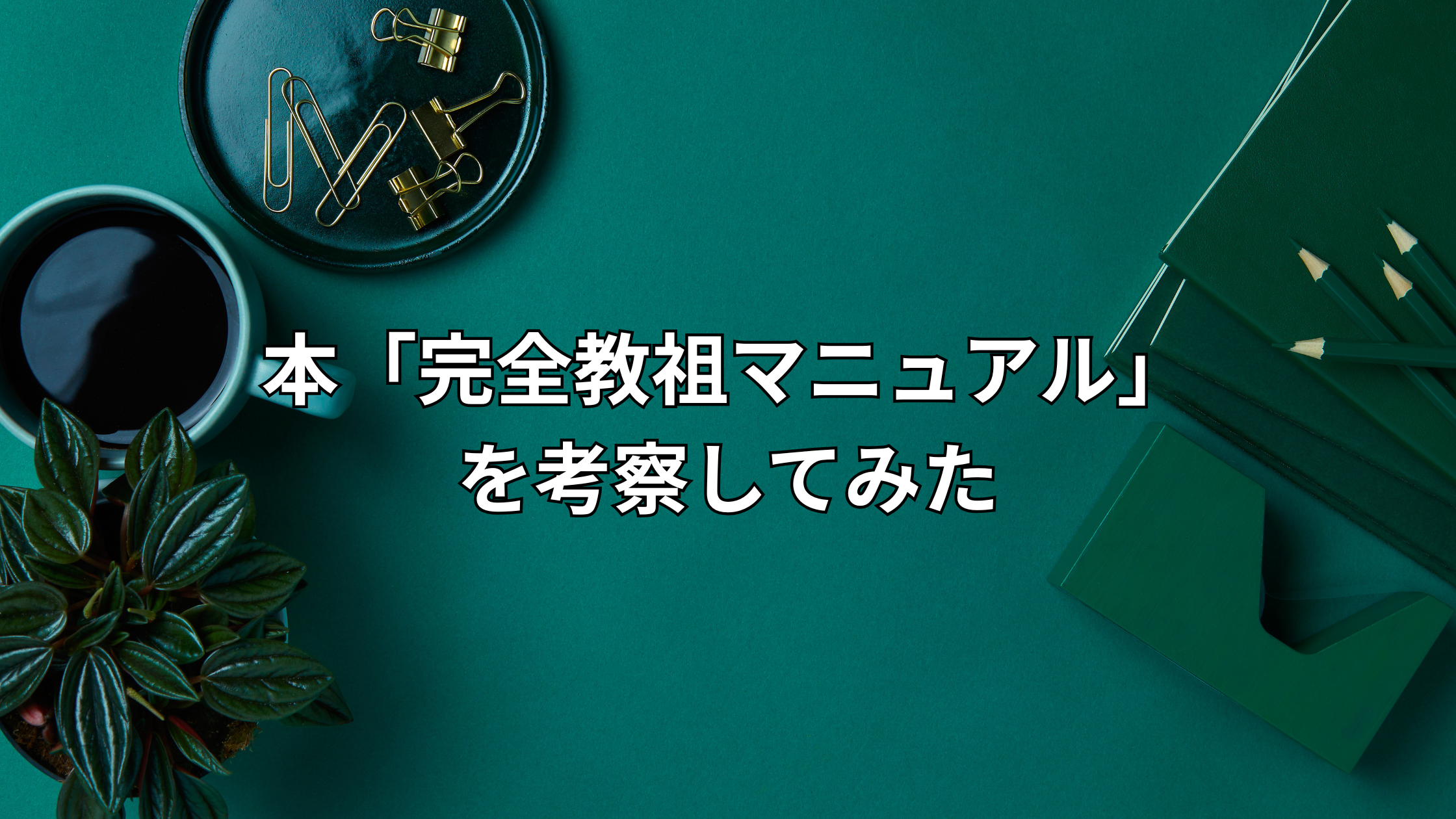
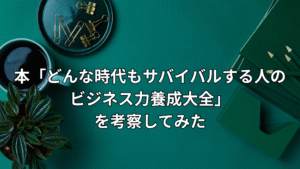
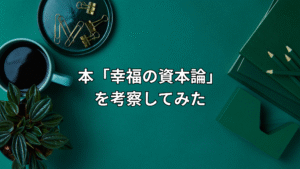
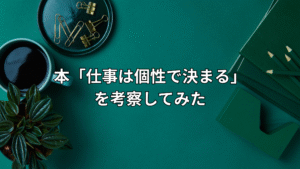
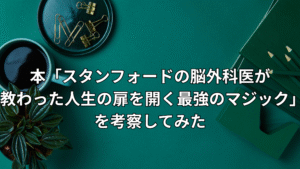

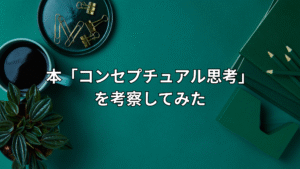
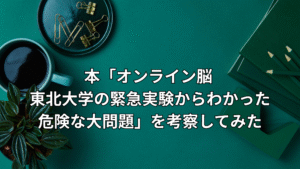
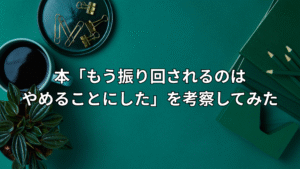
コメント