中野信子さんの著書『科学がつきとめた運のいい人』は、「運」という目に見えないものを、脳科学の視点から明快に解き明かしてくれる一冊です。
一見、偶然や神頼みに感じられる“運”ですが、本書を読むと、その正体は意外とシンプルで、誰にでも手に入れられるものであることがわかります。
ここでは、運の良し悪しが決まる3つのポイントについて、考察を深めていきます。
考察① 自分を大切にすることで運の受け取り力が上がる
自分自身を大事にできる人ほど、運をつかみやすい。
これは、自己肯定感が高い人は心に余裕があり、周囲の変化やチャンスに気づきやすくなるからです。
たとえば、疲れすぎていたり、いつも自分を責めていたりすると、視野が狭くなりやすい。
その結果、せっかく運が巡ってきても見逃してしまうことがあります。
逆に、しっかり休息を取り、自分を認めてあげている人は、環境を正しく認識できます。
すると、チャンスに敏感になり、それを自然とキャッチできるようになるのです。
「運がいいかどうか」は、実は偶然の差ではなく、自分をどう扱っているかの差。
日々の小さな習慣が、未来の運に繋がっていくことをこの考察から実感できます。
考察② 「自分は運がいい」と思い込む人が、運を引き寄せる
「私は運がいい」と思っている人の多くは、本当に運がいい出来事を引き寄せています。
これは単なる楽観主義ではなく、脳の性質が関係しています。
人は、自分が信じている情報ばかりを集める「確証バイアス」というクセがあります。
つまり、「自分は運がいい」と思っていれば、脳はそれを裏付ける出来事ばかりを集め始めるのです。
たとえば、雨に濡れた日でも、「たまたま濡れただけ」と流せる人もいれば、「やっぱり自分はツイてない」と落ち込む人もいます。
出来事は同じでも、捉え方によって「運の良し悪し」の印象がまるで変わってしまう。
大切なのは、日々の出来事に対して「これはラッキー」と思える習慣を持つこと。
それが運を引き寄せる力を高めてくれるのです。
考察③ 他人とのつながりが、運を大きく左右する
運がいい人は、自分ひとりで運を引き寄せているわけではありません。
周囲との関係性を大切にし、人と“共に生きる”姿勢を持っています。
人との信頼関係があると、良い情報やチャンスが自然と集まりやすくなります。
また、いざというときに誰かが手を差し伸べてくれることも多い。
反対に、他人を蹴落とすような考え方では、短期的に得をすることがあっても、長い目で見れば孤立しやすく、運も逃げていってしまう。
たとえば、職場で同僚にちょっとした親切をしていたら、後日その人が大きなプロジェクトにあなたを推薦してくれた。
こういった出来事は、「人とのつながり」が生んだ運のひとつです。
運とは、単なるラッキーではなく、人との間にある“信頼の貯金”が生み出すもの。
人間関係を大切にすることが、未来の運の基盤になります。
まとめ
『科学がつきとめた運のいい人』が教えてくれるのは、「運は平等に降り注いでいるが、それを受け取れるかどうかは自分次第だ」ということです。
運をつかむには、まず自分自身を大切にすること。
そして、「自分は運がいい」と信じる思考を持ち、人との関係を大切にすることが鍵になります。
この本を読むと、「運は生まれつきのものじゃない。育てていけるものなんだ」と前向きになれます。
日々の小さな意識が、未来の幸運を引き寄せることにつながっている──そんな気づきを与えてくれる一冊です。
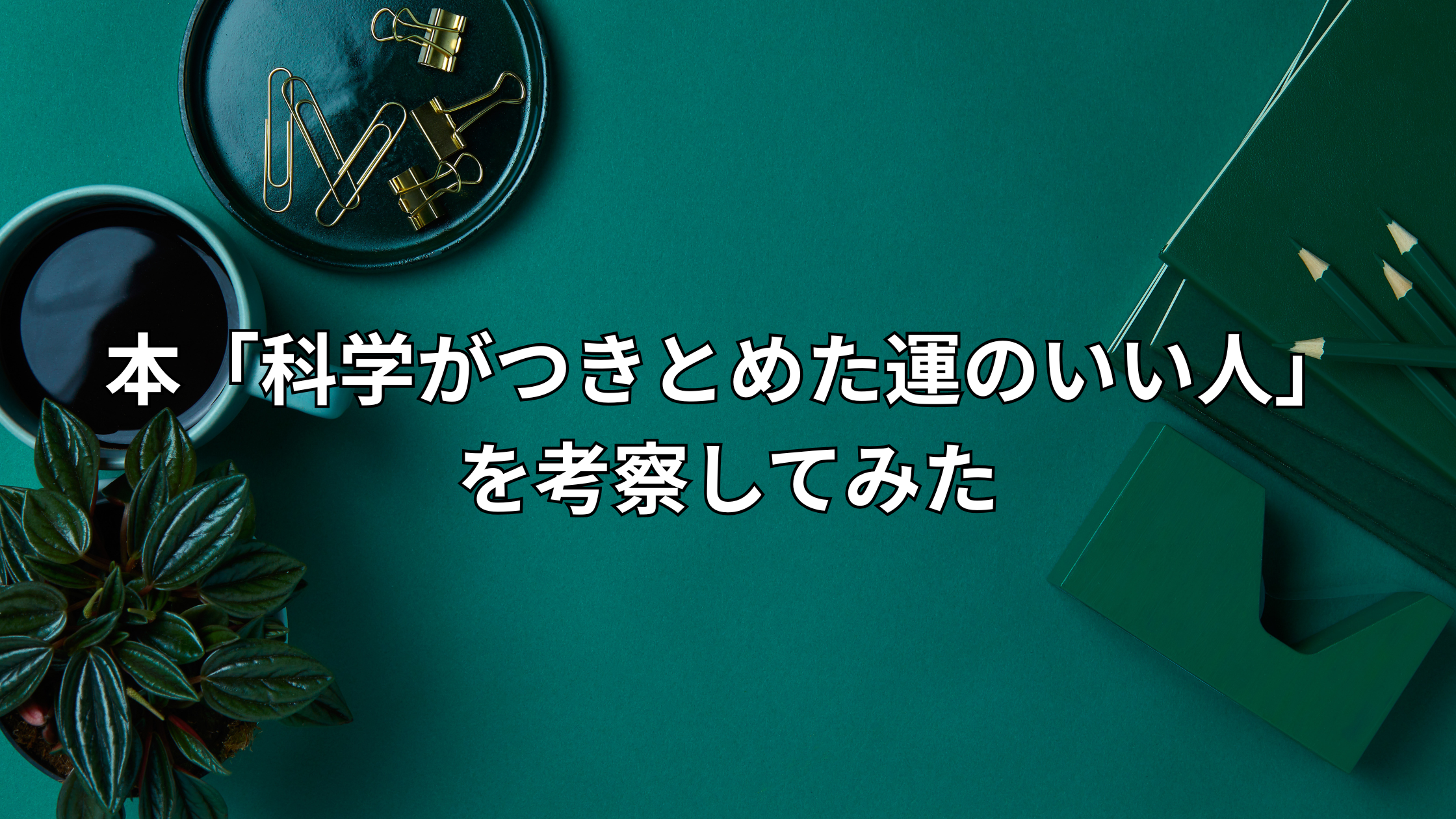
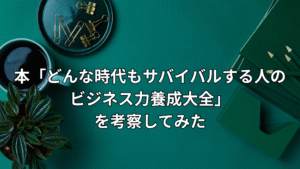
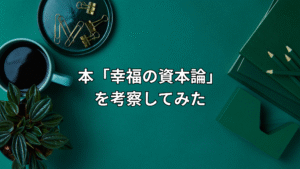
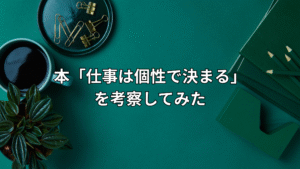
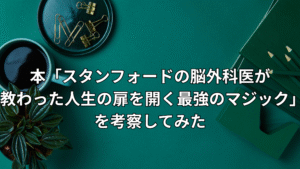

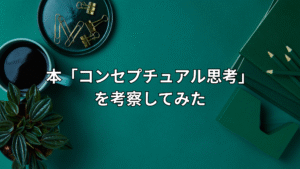
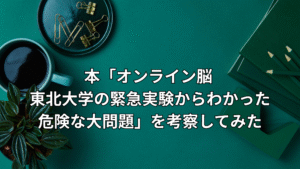
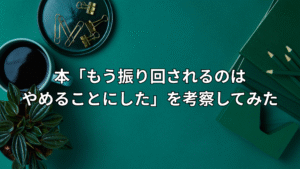
コメント