私たちが毎日何気なく口にしている食品。
その中に、健康に影響を及ぼす“見えないリスク”が潜んでいるとしたらどう思いますか?
スーパーやコンビニに並ぶ商品は便利で美味しい反面、食品添加物や加工方法の違いによって、身体への負担が大きく変わることもあります。
今回ご紹介するのは、そんな食の選択を「どっちが安全?」という視点で分かりやすく教えてくれる一冊――『令和版 食べるなら、どっち!?』(著:渡辺雄二)です。
この記事では、実際に本を読んで感じたポイントや、今後の食生活で意識したい点を3つの考察に分けてお届けします。
考察① 健康における最大の落とし穴
食品添加物は「知らないうちに摂っている」ことが最大のリスクだと感じました。
普段、私たちが何気なく食べているコンビニのおにぎりや加工食品。
その多くに、実はたくさんの添加物が使われています。
例えば、ハムやソーセージに使われる「亜硝酸ナトリウム」。
見た目をきれいに保つための成分ですが、体内で強い発がん物質「ニトロソアミン」に変化する可能性があるといわれています。
ただし、それを食べたからといってすぐに健康被害が出るわけではありません。
それが逆にやっかいなところです。
一度でダメージが出ないぶん、「まあ大丈夫か」と油断しがち。
でも、それを日々積み重ねていくと、将来的に健康リスクが高まるかもしれない。
その「静かなリスク」に気づかされる一冊でした。
考察② 「どっちを選べばいいか?」がすぐにわかる
本書の優れた点は、「結局どっちを選べばいいのか?」を具体的に教えてくれるところです。
食品に対する本や情報はたくさんありますが、読者が実生活に活かせるような視点で書かれているものは意外と少ないです。
一方この本では、スーパーやコンビニで見かける商品を取り上げながら「選び方のコツ」を紹介してくれます。
たとえば、「コンビニのポテトサラダと、手作りのサラダ、どちらがいいか?」という比較。
こういう日常の選択肢をベースにしているので、すぐに生活に取り入れることができます。
また、食品の裏に書かれた「原材料名」のチェックポイントもとても実践的です。
カタカナがずらりと並ぶ加工食品や、糖質が多い「ぶどう糖果糖液糖」が目立つ商品は避けるなど、判断基準が明確です。
知識を得るだけでなく、「今日から変えられる行動」に落とし込めるのがこの本の大きな魅力だと感じました。
考察③ 完璧を求めすぎない
「安全な食品選び」は、完璧を求めすぎないことも大切だと思います。
この本を読んでいると、つい「あれもダメ、これも危険」と思ってしまいがちです。
でも現実には、外食もすれば、加工食品を手に取ることもあります。
そうした日常の中で、すべての添加物を避けることは現実的ではありません。
だからこそ、「毎回100点を取るのではなく、60点を積み重ねる」意識が必要です。
たとえば、アイスを食べるならカラフルなものよりシンプルな氷菓子にする。
ポテチを買うなら、材料が少ないシンプルなものを選ぶ。
完璧を目指さず、「できるときに、できるだけ良い選択をする」だけでも、健康への影響は大きく違ってくるはずです。
本書も、その点を強く押し付けるのではなく、ゆるやかに「選ぶ力」を育てるスタンスで書かれています。
それがまた、長く付き合っていける食習慣につながるのだと感じました。
まとめ
『令和版 食べるなら、どっち!?』は、健康意識を高めたい人にとって非常に実用的な一冊です。
食品添加物の存在に気づき、日常で少しずつでも選び方を変えていく。
その積み重ねが、将来の自分と家族の健康を守ることにつながります。
完璧でなくてもいい。
でも、「知っているか知らないか」で選択の質は大きく変わる。
そんな気づきを与えてくれる、読み応えのある内容でした。

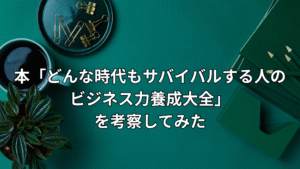
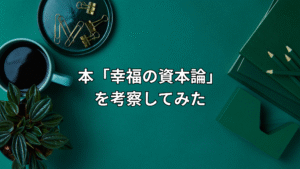
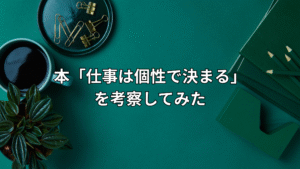
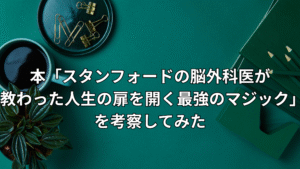

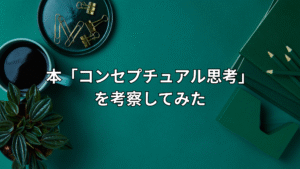
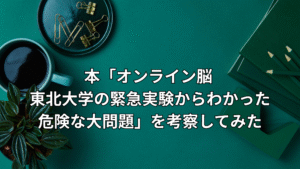
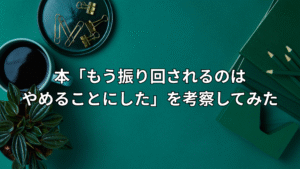
コメント