「1日1杯脳のおそうじスープ」は、脳の健康を維持するための食事法を提案する一冊です。
特に、脳に蓄積する「ゴミ」ともいわれるアミロイドベータを効率よく排出するためのスープレシピが紹介されています。
本書を読むことで、食生活の改善が脳の働きにどのような影響を与えるのかが明確になります。
今回は、本書の内容を踏まえ、3つの視点から考察を行います。
考察① 脳のゴミはどうやって排出されるのか
脳の健康を保つためには、アミロイドベータの除去が不可欠です。 この物質が蓄積すると、認知症のリスクが高まるとされています。
脳のゴミを排出する鍵となるのが「グリンパティックシステム(脳内の排出機能)」です。 これは睡眠中に活性化し、不要な老廃物を洗い流す役割を果たします。
本書では、この排出機能を最大限に活かすために、食事の工夫が重要だと述べられています。 特に、スープは水分補給と栄養摂取を同時に行え、脳のクリーニングに適した食品です。
食事を通じて脳の健康をサポートすることは、日常的に実践しやすく、誰にでも取り入れやすい方法といえます。
考察② スープが脳に与える影響
スープを摂取することが、なぜ脳の健康に良い影響を与えるのかを考えます。
スープは消化吸収がしやすく、体に負担をかけずに必要な栄養素を摂取できるという利点があります。 特に、本書で推奨されるスープには、抗酸化作用のある食材や良質な脂質が豊富に含まれています。
例えば、オメガ3脂肪酸を多く含む食材(サバ、アマニ油など)は、脳の神経細胞を保護する役割があります。 また、野菜や発酵食品を取り入れることで、腸内環境を整え、脳との相互作用(腸脳相関)を高めることができます。
これらの要素が合わさることで、スープを飲むことが脳機能の維持・向上につながると考えられます。
考察③ 実践しやすい食事法としての魅力
健康的な食事法は続けることが大切ですが、手間がかかると継続が難しくなります。 その点、本書で紹介されるスープは手軽に作れるものが多く、日々の食生活に取り入れやすいのが魅力です。
例えば、具材を切って煮込むだけのシンプルなレシピが多いため、料理が得意でない人でも無理なく実践できます。 また、一度に多めに作って保存しておけば、忙しい日でも簡単に栄養を補給できます。
さらに、スープはアレンジがしやすく、自分の好みに合わせて食材を変えられる点もポイントです。 この柔軟性があることで、飽きずに続けやすくなります。
手軽さと継続のしやすさが、本書の提案する食事法の大きな利点といえます。
まとめ
「1日1杯脳のおそうじスープ」は、脳の健康を守るための実践的な食事法を提案する一冊です。 脳のゴミを排出するメカニズムを理解し、スープを活用することで、認知機能の維持や向上が期待できます。 また、シンプルで継続しやすいレシピが多く、誰でも無理なく取り入れられるのも魅力です。
食生活を見直し、日々の食事に脳を意識した工夫を取り入れることで、長期的な健康につなげていくことができるでしょう。 この本を参考に、ぜひ「脳のおそうじスープ」を試してみてはいかがでしょうか。
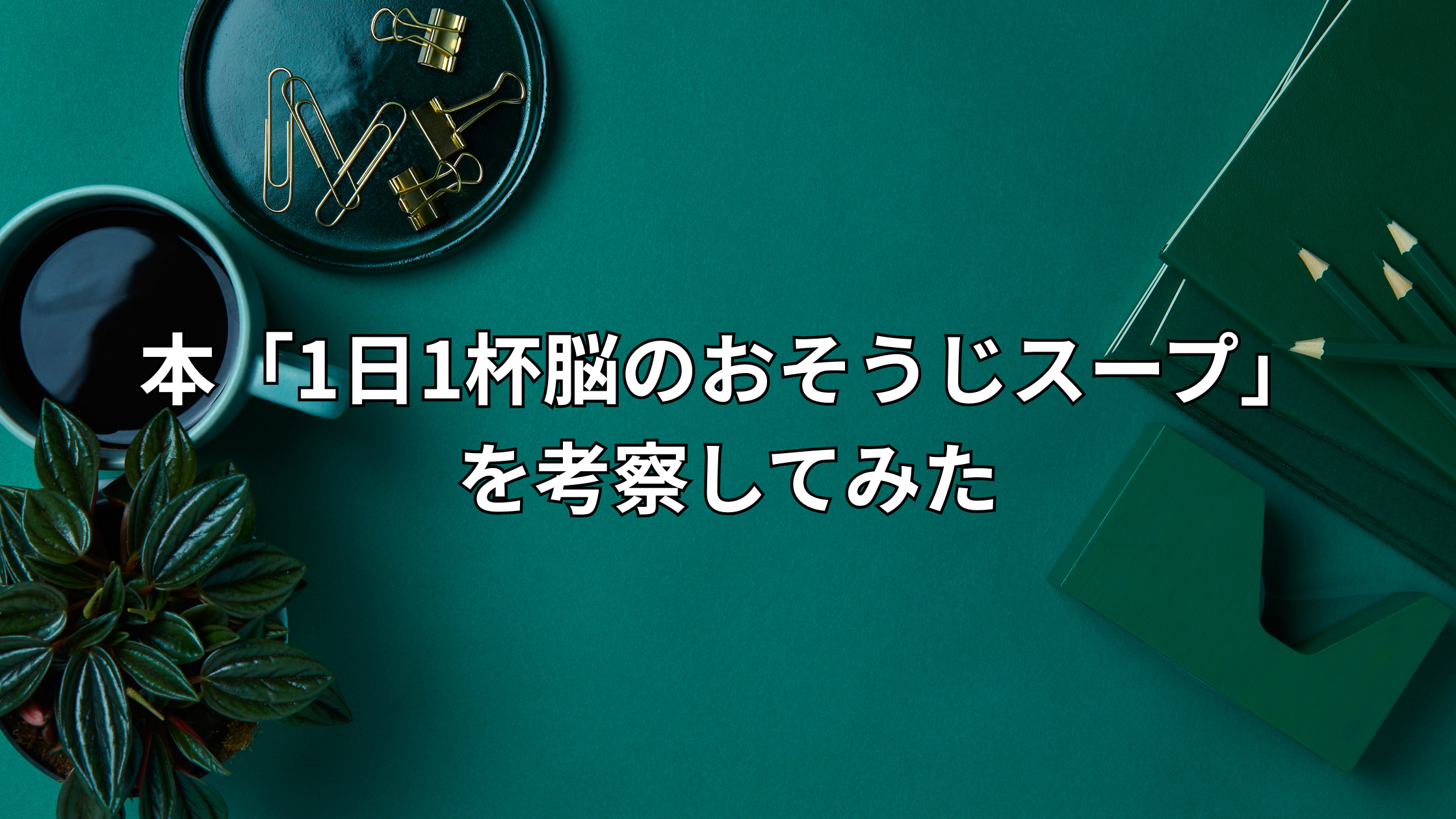
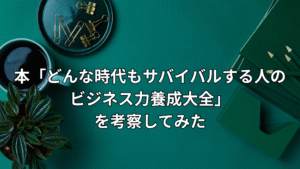
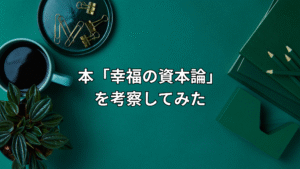
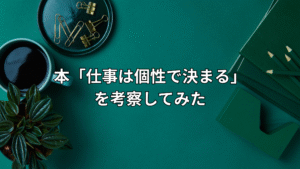
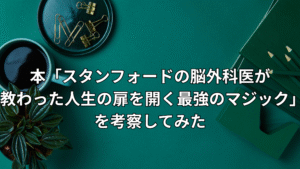

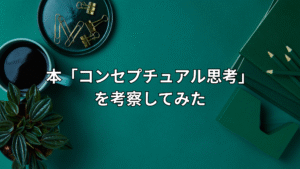
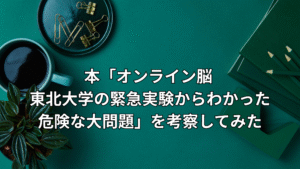
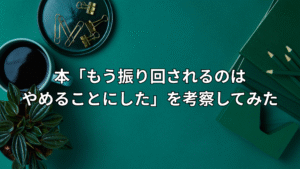
コメント