私たちは毎日、睡眠をとることで体と心を回復させています。
しかし、どれだけ寝ても疲れが取れない、日中にぼんやりしてしまうと感じる人は少なくありません。
そんな悩みを持つ方にとって、本書『自分でできる! 熟睡脳のコツ』(著:酒谷薫)は、眠りの質を見直すきっかけとなる一冊です。
本記事では、本書の内容をもとに、熟睡脳をつくるための重要なポイントを3つの観点から考察していきます。
考察① 「脳を休ませる」意識を持つことが、眠りの質を変える
睡眠は単なる休息ではなく、脳の回復時間です。
この視点を持つことで、日常の睡眠に対する考え方が変わってきます。
現代では、睡眠時間を削って作業することが美徳のように扱われる場面もあります。
しかし本書は、睡眠を「脳の健康を守るための活動」として捉え直すことの重要性を伝えています。
たとえば、睡眠不足になると脳内に老廃物が溜まり、集中力や判断力が低下します。
これは、脳の掃除機ともいえる「グリンパティック系」が十分に働かないことが原因です。
しっかりと脳を休ませる睡眠を意識するだけで、日中のパフォーマンスは大きく変わってくるのです。
考察② 寝つきをよくするには「副交感神経」への切り替えがカギ
眠れない原因の多くは、脳が興奮状態のままベッドに入っていることにあります。
その状態から自然な眠りに入るには、自律神経のスイッチを「副交感神経優位」に切り替えることが大切です。
本書では、深い呼吸や軽いストレッチ、照明の調整など、脳をリラックスさせる具体的な行動が紹介されています。
たとえば、就寝1時間前にはスマホを手放し、暖色系の照明に切り替えることで、脳に「夜が来た」と認識させることができます。
また、「眠ろうとしないこと」も重要なポイントです。
眠らなきゃと焦るほど交感神経が優位になり、かえって眠りを妨げてしまいます。
副交感神経にスムーズに切り替える習慣を持つことで、無理のない自然な眠りへと導かれるのです。
考察③ 「日中の過ごし方」が夜の眠りを左右する
熟睡するためには、夜だけに意識を向けるのでは不十分です。
日中の活動こそが、夜の睡眠の質を決定づけます。
本書では、「脳の疲労感」と「程よい体の疲れ」をつくることのバランスが重要だとされています。
たとえば、運動不足だと体が眠る準備を整えられず、逆に脳だけが疲れて眠りが浅くなってしまいます。
日中に適度な運動を取り入れたり、朝に太陽の光を浴びて体内時計を整えることは、夜の快眠につながります。
また、カフェインや昼寝の取り方など、細かい生活習慣も見直すポイントとなっています。
夜の眠りを良くするには、朝から始まる1日の過ごし方が大きく影響しているのです。
まとめ
『自分でできる! 熟睡脳のコツ』は、眠りの質を上げたいすべての人に役立つ一冊です。
脳を休ませる意識を持つこと、副交感神経への切り替え、日中の過ごし方の見直しという3つの視点から、私たちができる改善策が丁寧に紹介されています。
眠れない原因を「体」ではなく「脳」にフォーカスして考えることは、これまで見落としていた大きな視点の転換になるはずです。
毎日の眠りを少しずつ変えていくことで、心も体もすっきりと目覚める朝を迎えることができるようになります。

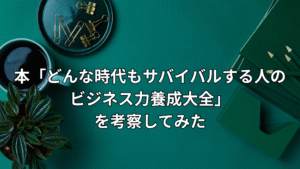
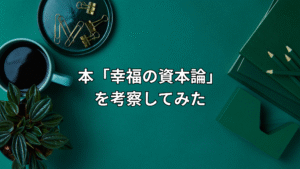
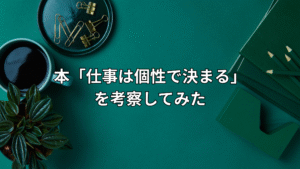
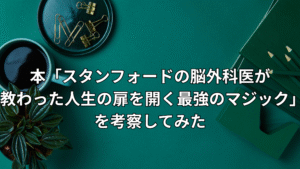

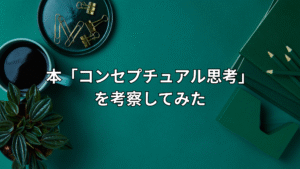
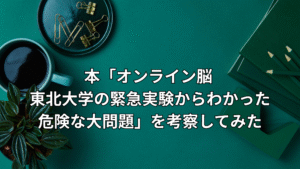
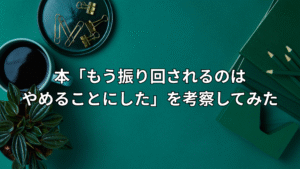
コメント