インターネットやスマホが生活に欠かせない時代。
便利さの裏で、私たちの脳にはどんな変化が起きているのでしょうか。
本書『オンライン脳 東北大学の緊急実験からわかった危険な大問題』は、脳科学者・川島隆太氏が、科学的なデータをもとにそのリスクを明らかにしています。
とくに子どもたちの脳にどのような影響が出ているのか。
そして、それが将来にどんな問題を引き起こす可能性があるのか。
本記事では、本書を読んで考えた3つのポイントについて掘り下げていきます。
考察①:スマホの使いすぎが脳の発達を妨げる
スマホの長時間使用が、子どもの脳に悪影響を与えることは、以前から指摘されてきました。
しかし、本書では「東北大学による実験データ」をもとに、その危険性が明確に示されています。
特に問題視されているのが、前頭前野という脳の部位。
ここは人間の思考、判断、集中、感情のコントロールに関わる重要な領域です。
スマホ操作ではこの前頭前野がほとんど使われないため、子どもの脳の発達が十分に促されないのです。
著者である川島隆太氏は、長年にわたり脳科学の研究を行ってきた人物です。
彼の実験では、スマホの使用時間が長い子どもほど、学力や集中力が明らかに低下していることが確認されました。
つまり、子どもの「使い方次第」で、将来的な能力が左右されてしまうということです。
スマホの普及によって便利さが増す一方で、発達段階にある子どもたちの脳には深刻な影響が出ている可能性があります。
だからこそ、家庭や学校でのルール作りが、今後ますます重要になっていくでしょう。
考察②:大人の脳も“使わないことで”衰えていく
スマホ脳の問題は、子どもだけに限りません。
大人にとっても、長時間のスマホ使用が「脳の老化」を早める可能性があると指摘されています。
日常的にスマホでニュースを見たり、SNSを眺めたりするだけでは、脳の深い思考はあまり必要とされません。
これが習慣になると、脳の使う領域が限定され、機能が衰えていくのです。
川島氏は「脳は使わなければ衰える」と繰り返し述べています。
特に思考力や記憶力が落ちてきたと感じる人ほど、スマホに頼らない時間を意識的に作るべきです。
たとえば、日記を書く、計算をする、音読をするなど、シンプルな行動でも脳への刺激になります。
便利さと引き換えに、私たちは「考えなくても済む」環境に慣れつつあります。
だからこそ、自分の意志で「脳を使う時間」を確保することが大切です。
考察③:デジタル教育は“導入方法”がすべてを左右する
コロナ禍以降、教育現場でも急速にデジタル化が進みました。
タブレット学習やオンライン授業の導入は、確かに効率性を高めましたが、その裏には見落とされがちなリスクもあります。
本書では、タブレットを活用する時間が長くなるほど、子どもたちの学力が下がる傾向にあることが実験で示されています。
これは「デジタルが悪い」という話ではありません。
問題なのは、デジタル機器が“どう使われているか”です。
受け身で動画を見るだけの授業や、検索して答えを写すだけの学習では、脳はほとんど働きません。
逆に、ディスカッションや発表など、自ら考えてアウトプットするスタイルであれば、デジタルでも脳の活性化は可能です。
つまり、教育現場でのデジタル活用は「質」が問われる時代に入っているのです。
機械に頼るのではなく、「人の頭を使う場面をどう作るか」が鍵になります。
まとめ
本書を通じて、私たちの生活に深く入り込んだデジタル機器が、脳に与える影響の大きさを改めて実感しました。
便利なツールだからこそ、使い方を間違えれば、子どもも大人も大きな代償を払うことになります。
だからこそ、私たちは「情報に触れる時間」よりも「どう脳を働かせるか」を意識して生活するべきです。
スマホやタブレットと賢く付き合うためには、ルールとバランス、そして“脳を守る視点”が必要です。
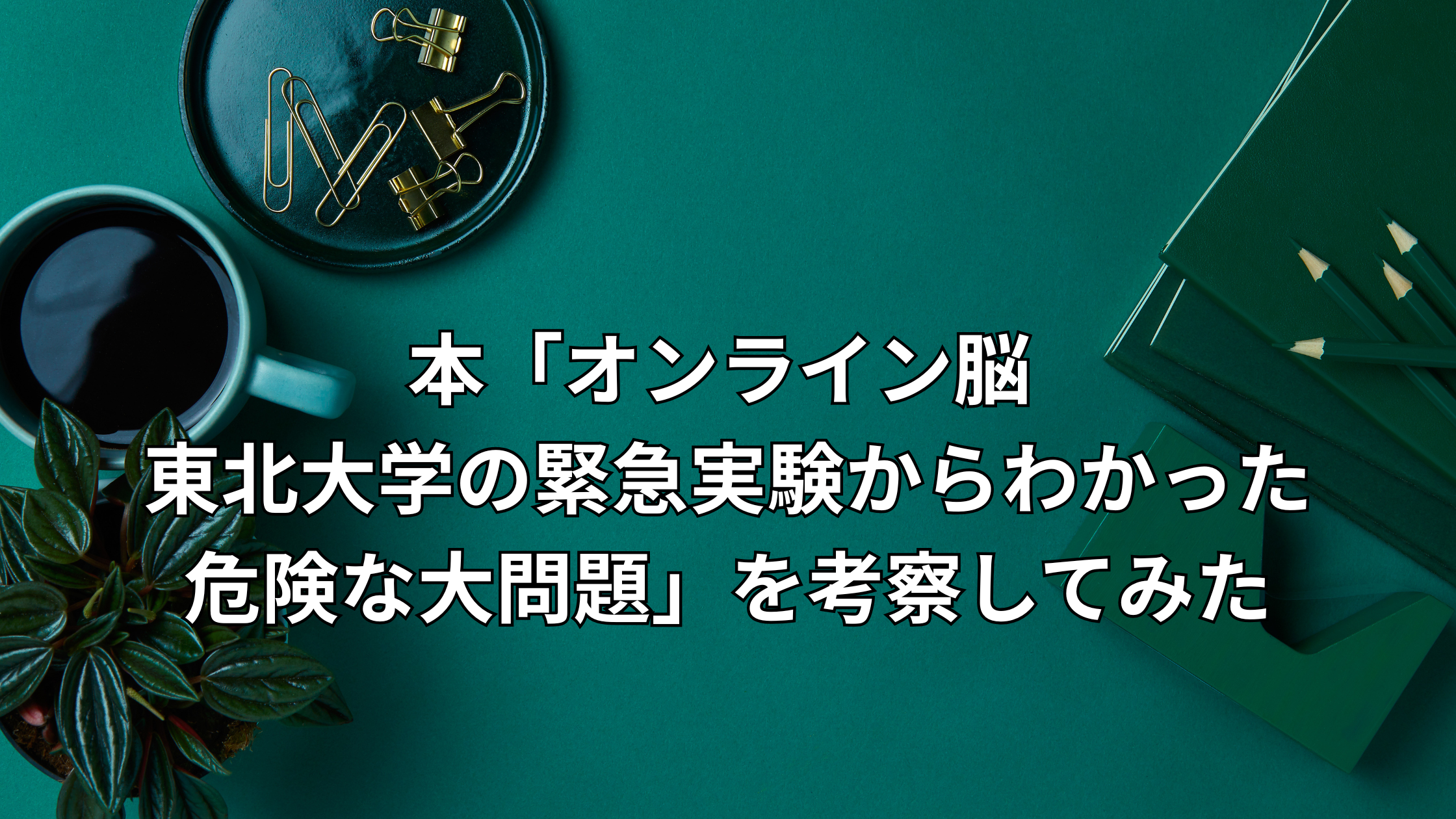
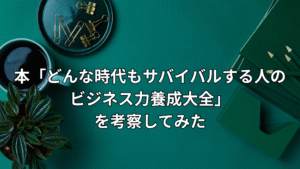
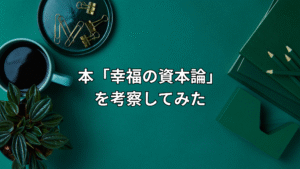
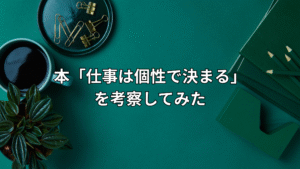
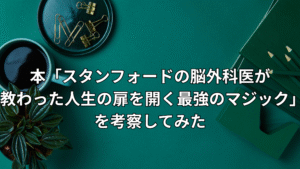

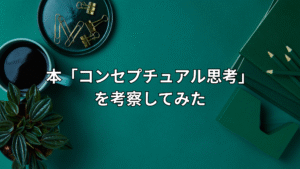
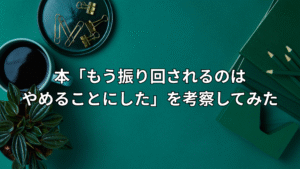
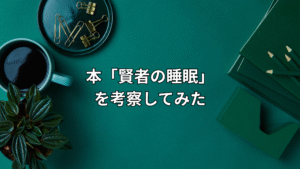
コメント