「頑張っているのに成果が出ない」と感じたことがある人は多いと思います。
本書『エフォートレス思考』は、そんな人に向けて“がんばらない成功法則”を提案する一冊です。
ただのラクのすすめではなく、本当に大切なことに集中するための頭の使い方・行動の工夫・仕組みの作り方が語られています。
今回はこの本の要点を3つの視点から考察していきます。
考察①「努力=正解」という思い込みが行動の妨げになる
努力が美徳とされる文化の中で、多くの人が「苦労しないと成果は出ない」と思い込んでいます。
しかし著者は、それがかえって行動のハードルを高くしてしまうと指摘します。
「頑張らなきゃいけない」と思うほど、物事が重く感じられて動けなくなる。
これは多くの人が無意識にハマっている落とし穴です。
たとえば、資格勉強に取り組む人が「毎日2時間やらなきゃ意味がない」と考えると、やる気が出ない日はそのままやらずに終わってしまうこともあります。
でも「5分でもいいから参考書を開こう」と考えるだけで、行動のハードルがぐっと下がる。
そして実際にやってみると、気づけば20分、30分と続いていることもあるものです。
つまり、成果を出すためには「どれだけ頑張れるか」よりも「いかにラクに始められるか」が大事だということ。
努力の質を見直すことで、もっと軽やかに進める可能性があると気づかされます。
考察②「楽しさ」が行動を継続させる原動力になる
本書の中で特に印象的なのは、行動に“楽しさ”を加えるという考え方です。
人はつらいことを避け、楽しいことに引き寄せられる性質を持っています。
だからこそ、義務感で何かを続けようとしても長続きしないのは当然とも言えます。
著者は、行動を“儀式化”することや、ちょっとした報酬を結びつけることで行動が楽になると語っています。
たとえば、毎朝のメールチェックが億劫だと感じている人が、チェックの時間にお気に入りのコーヒーを淹れると決める。
「コーヒーを飲みながらメールを見る」がルーティンになることで、行動のハードルが下がるのです。
こうした小さな工夫の積み重ねによって、「面倒だ」と思っていたことがいつの間にか習慣になります。
楽しさを軸にすることは、意志力に頼らず行動を継続するための鍵になると感じました。
考察③ 成果を積み上げる仕組みを持つことが人生をラクにする
一時的な努力で成果を得るのではなく、持続的に成果が出る「仕組み」を作る。
これが、エフォートレス思考の最も強力な部分です。
たとえば、1対1の仕事は「直線的な成果」です。
働いた分だけ成果が出るけれど、それは時間を売っているに過ぎません。
対して、動画や記事、システムなどを作っておけば、あとは自動で成果が出る「累積的な成果」になります。
コンテンツを資産に変える、作業を自動化する、ルールを決めて迷いを減らす。
こうした仕組み化は最初こそ手間がかかりますが、後々の自分を大きく助けてくれます。
特に、忙しさに追われがちな現代人にとっては、仕組みを整えること自体が“余裕”を生む行動だと思います。
仕組みを味方につけることは、努力をしなくても成果が続く状態をつくる第一歩になるのです。
まとめ
『エフォートレス思考』は、「もっと頑張らなきゃ」と思っている人ほど読むべき本です。
努力の方向を間違えずに、成果が自然と出る仕組みを整えること。
そして、楽しさやラクさを味方につけることで、継続しやすい行動スタイルを作っていく。
努力を否定するのではなく、“必要なところだけに力を使う”という考え方は、現代人にとって非常に実用的です。
頑張ることに疲れてしまったとき、少し立ち止まって「もっとラクにできる方法はないか?」と問いかけてみる。
その問いこそが、本書のエッセンスなのかもしれません。
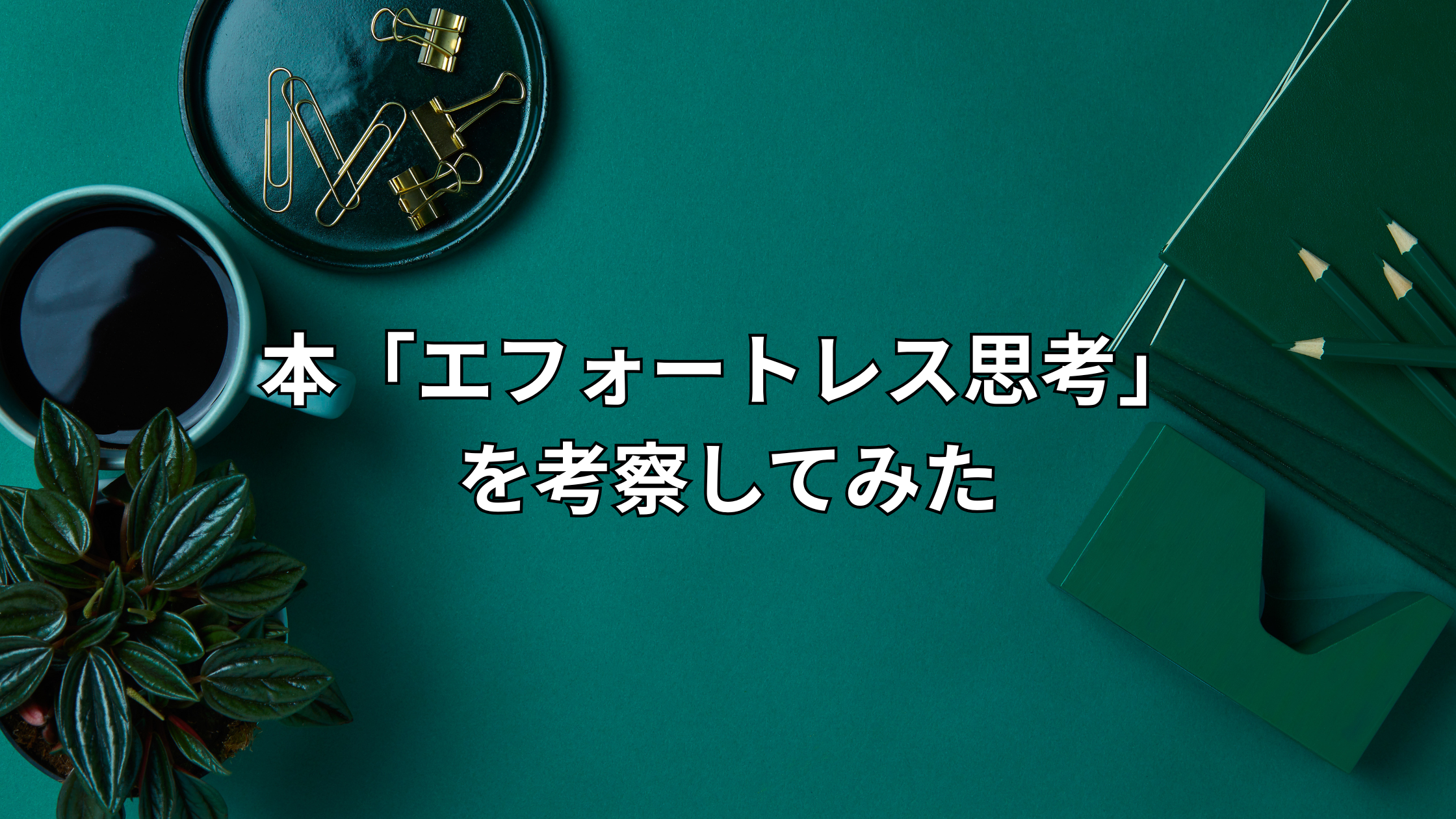
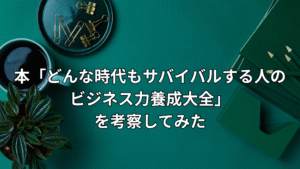
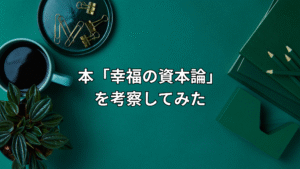
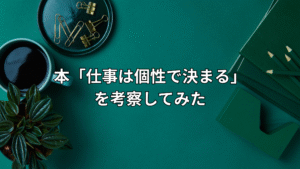
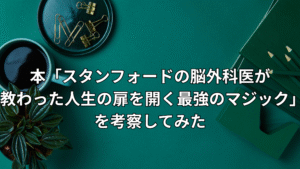

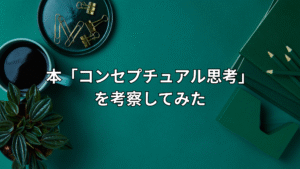
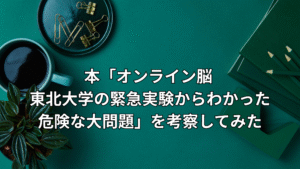
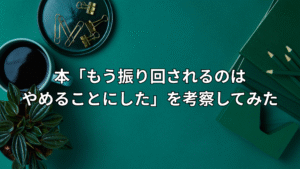
コメント